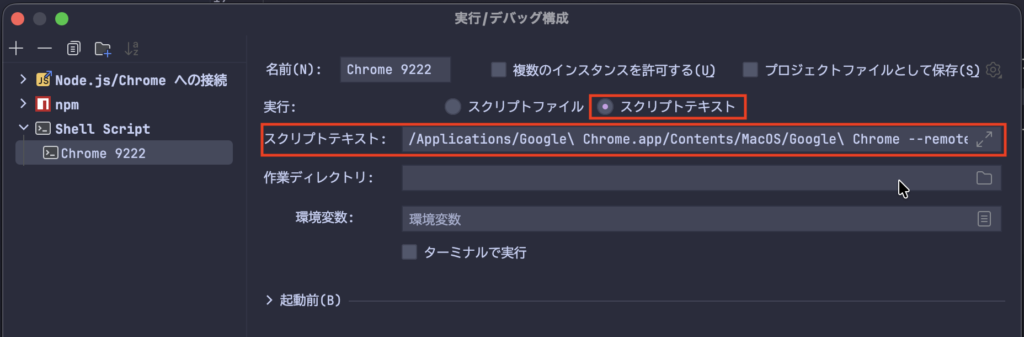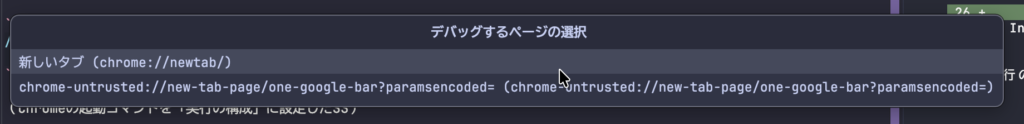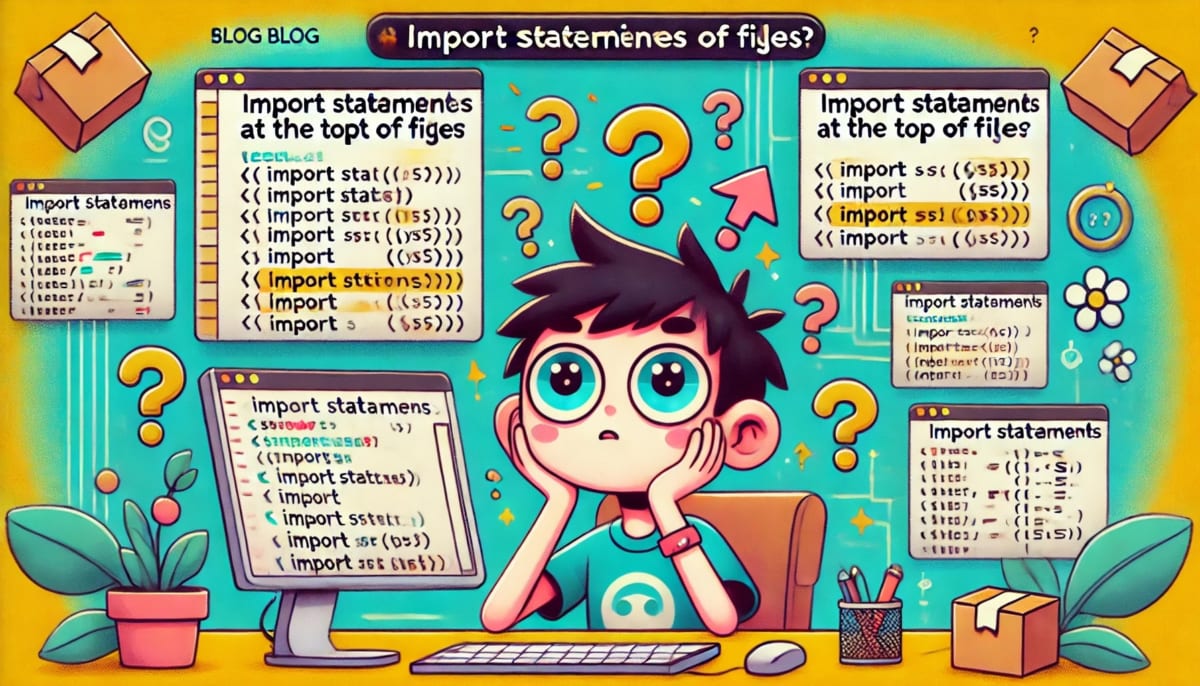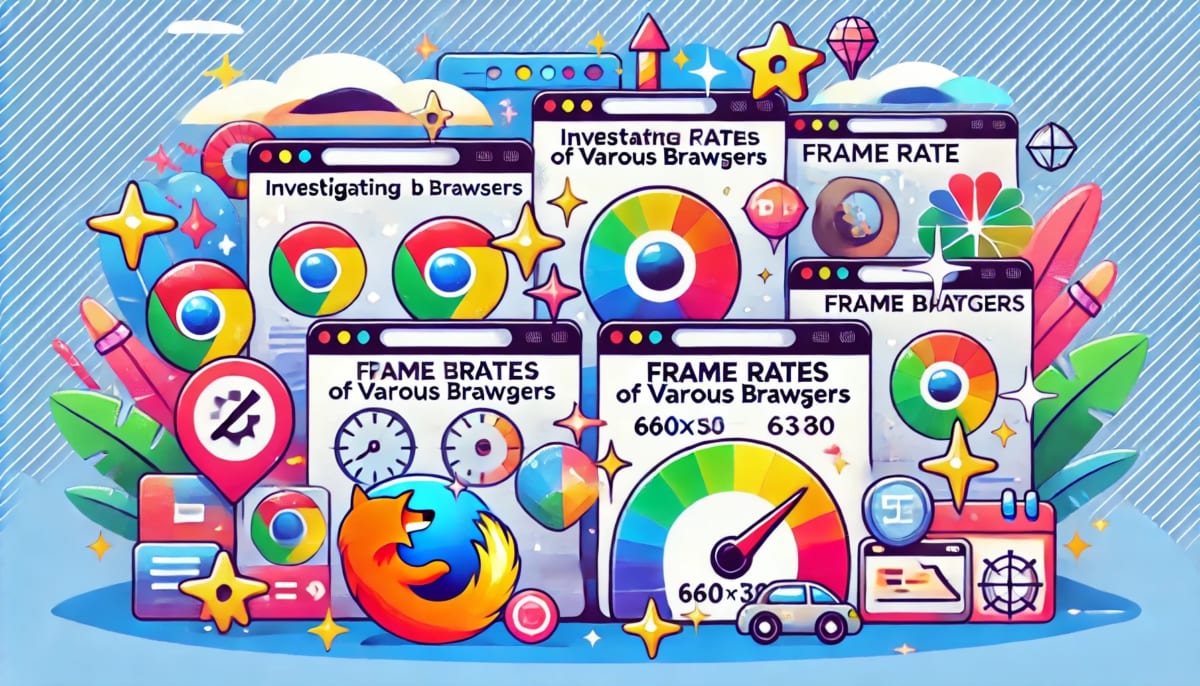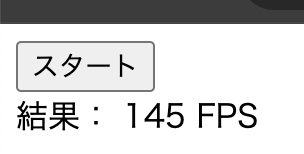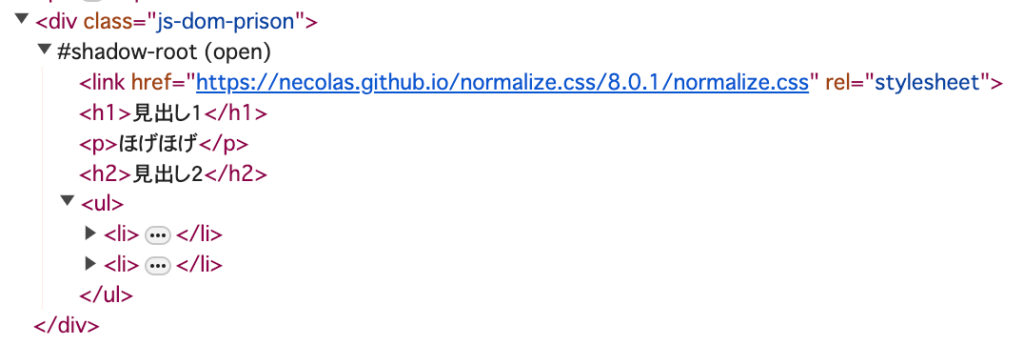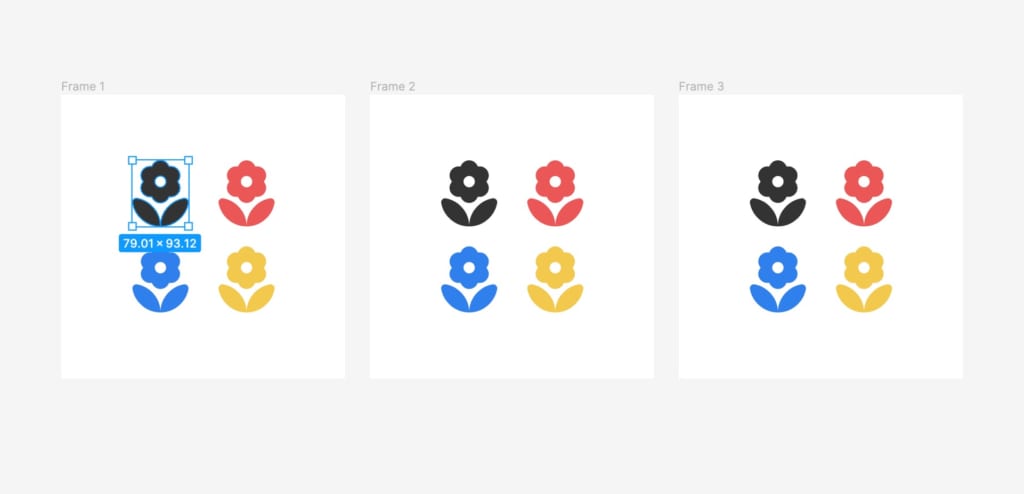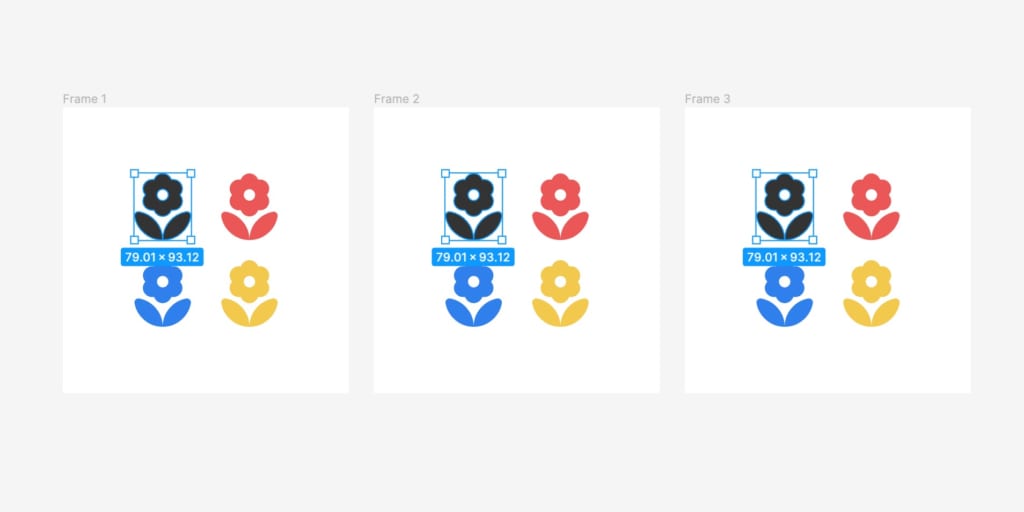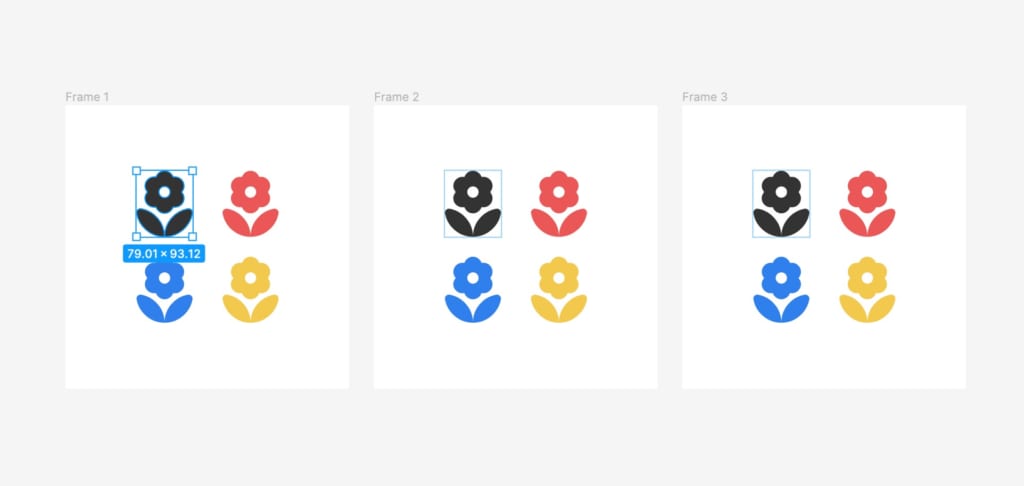始めに
今IT業界では、生成AIによってかつてないほどの大きな変動が起きています。
「AIがコードを書く時代」において、私たちWEBエンジニアには何が求められるのでしょうか?
単にAIにコードを書かせるだけではなく、AIをツールとして使いこなし、
開発速度や精度を劇的に向上させるための「新しいスキルセット」が必要とされています。
この記事では、スタンフォード大学が無料公開している講義資料について紹介します。
公式サイト(https://themodernsoftware.dev)
サイト内の「Syllabus」タブをクリックすると、各週の講義スライドやおすすめの関連記事を閲覧できます。
無料公開されているのはスライドと記事のみですが、非常に参考になる内容のため、今回紹介いたしました。
CS146S: The Modern Software Developer とは?
このコースは、スタンフォード大学で2025年秋学期に開講される「現代のソフトウェア開発者」のための授業です。
従来のプログラミング教育が「ゼロからコードを書く力」に重点を置いていたのに対し、
このコースではAIツールを前提とした開発ワークフローへと完全にシフトしています。
「これからの時代に必須となるスキルを身につけたい」というエンジニアの方は必見の内容です。
各週のテーマを日本語でまとめてみました:
Week 1: Introduction to Coding LLMs and AI Development
(コーディングLLMとAI開発への導入)
Week 2: The Anatomy of Coding Agents
(コーディング・エージェントの解剖学)
Week 3: The AI IDE
(AIネイティブなIDE)
Week 4: Coding Agent Patterns
(コーディング・エージェントのパターン)
Week 5: The Modern Terminal
(モダンなターミナル環境)
Week 6: AI Testing and Security
(AIによるテストとセキュリティ)
Week 7: Modern Software Support
(モダンなソフトウェア・サポート / レビュー・ドキュメント)
Week 8: Automated UI and App Building
(UIとアプリ構築の自動化)
Week 9: Agents Post-Deployment
(デプロイ後のエージェント活用 / 運用監視)
Week 10: What's Next for AI Software Engineering
(AIソフトウェアエンジニアリングの未来)
最後
今回の紹介は以上です。
サイトは英語のみですが、講義資料はスライド形式なので、翻訳ツールなどを使いながら読むだけでも非常に勉強になると思います。
また時間が取れたときに、それぞれの講義内容をまとめ記事も書くかもしれません。
参照リンク
公式サイト: themodernsoftware.dev
コースの課題:https://github.com/mihail911/modern-software-dev-assignments/tree/master